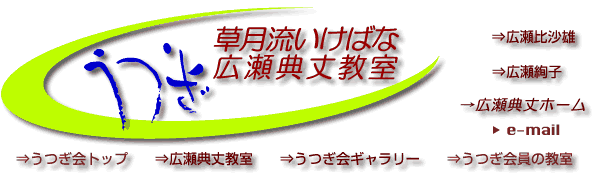
→広瀬典丈Webいけばな講座 →2 基本について8→基本について →技術 →自然調とは →古典花
|
 |
 ←Photo1 ふとい、ダッチアイリス ↑Photo2 、ふじばかま |
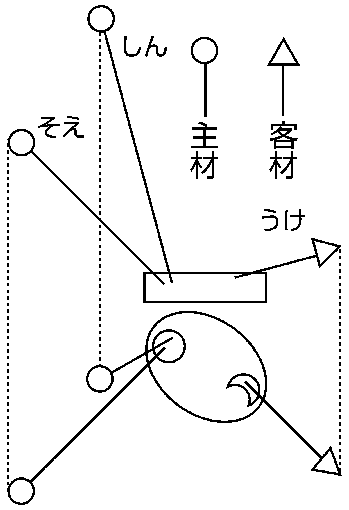 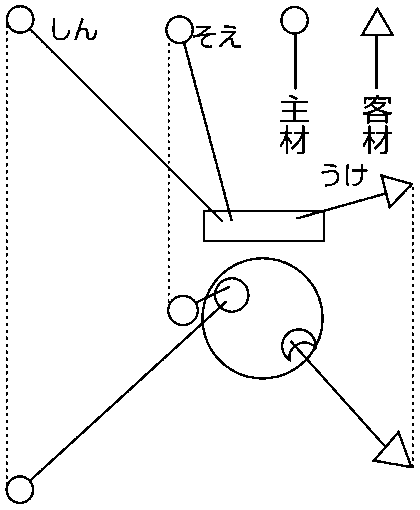 |
いけばなをいける時、一つにまとめられた根本を<株>と呼びます。また、水盤などで<株>を2つ以上に分けていけることを
(株分け)とか「二株にいける」と言うのです。(Photo1・2)▲
↑Photo3 、そけい、すかしゆり |
 ↑Photo4 、アリウム、アンスリウム、ぎぼし |
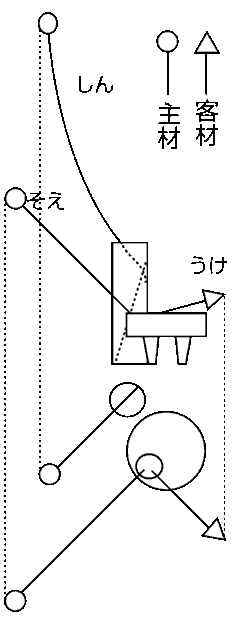 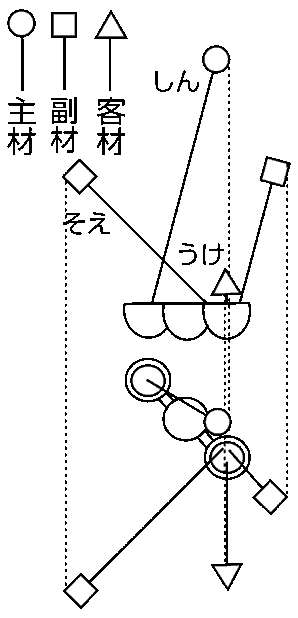 |
現在の (株分け)は、いけばなのバリエーションの1つで、どの季節にも自由にいけますが、歴史的には、水辺を映す夏の演出です。
花材を、<水もの>と<陸もの>(おかもの)、あるいは<水陸通用もの>などに分類し、左右を(水もの)でいけたり、水陸でいけ分けたりという趣向が好まれました。▲
(水もの)とは、水辺に生える植物、(がま・ふとい・かきつばた・はす・睡蓮・河骨など)、「陸もの」(おかもの)
とは、陸に生える植物一般です。「水陸通用もの」(すいりくつうようもの)とは、水辺にも陸にも育つ、荻・葦・花しょうぶなどを言います。▲
伝統的な手法に加えて、<うけ>にこだわらず、<しん>や<そえ>の
(株分け)、花器を複数使うなどの工夫で、さまざまな演習を重ねていくことが出来ます。差し口の狭い花器や、投入の(株分け)はありえないようですが、二つ以上の花器に一つの花型を活ける、つまり「花型の分解」など、展開の仕方では投入も使えます。
 ↑Photo5 、じんちょうげ、カラー |
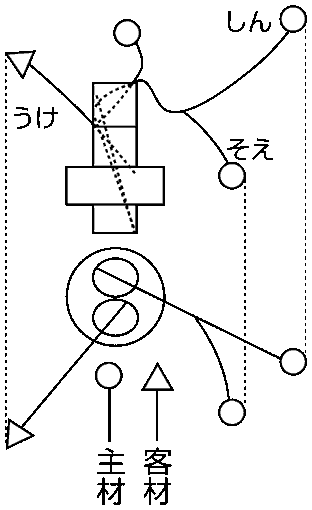 |
Photo3は、手前の足つき水盤に<そえ>と<うけ>を入れ、後ろに投入で<しん>を株分けした基本立真型。つまり、「花型の分解」です。Photo4は、3つの碗を並べたのではなく、つながった三口花器に、左右振り分けの<しん><そえ>と、真っ直ぐ前に倒れる<うけ>を組み合わせています。この作例でも株分けられているのは、アリウムで取った<しん>です。Photo5は、二口投入で、奥に一本のじんちょうげで(平真)・(垂副)と<しん><そえ>が入り、手前にカラーの<うけ>が株分けされています。▲
(2)「併合花型」
 ↑Photo6 、ふとい、くじゃく草、ひまわり |
 ↑Photo7 つるばら、しゃくやく |
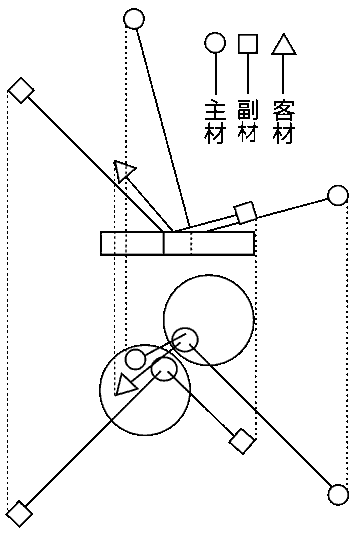 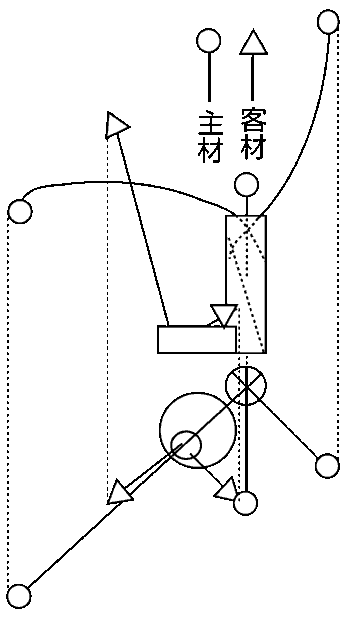 |
花型を二つ以上の花器にいけ合わせて、一つのいけばな作品にするのが『併合花型』です。花型の組み合わせはなんでもかまいませんが、たとえば片方を立真型にしたら、他方は傾真型にするなどして、同じ向き、長さの枝が平行に出ないような工夫が必要です。<役枝>の数が多すぎると思えば、一つを『省略花型』にするのもいいでしょう。▲
花材の組み方も、(主材)(枝もの)で<しん><そえ>、<客材>(草花)で<うけ>と固定せず、工夫すれば、効果的な『併合花型』ができます。(Photo6・7)
(3)「掛け花」と「吊り花」
 |
 ←Photo8 あざがお ↑Photo9 こでまり、ヒヤシンス |
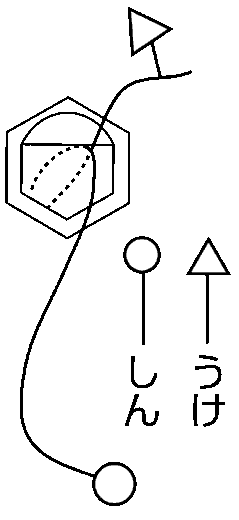 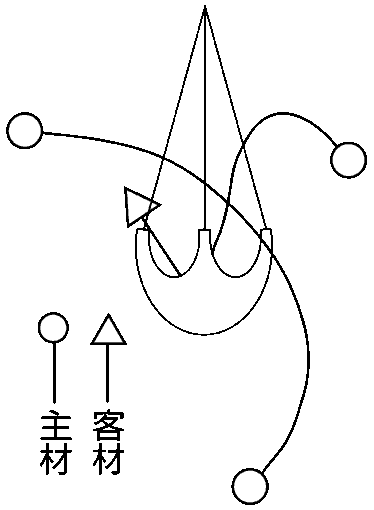 |
いけばなでは、「掛け花」・「吊り花」も昔から重視され、多くの「伝承花」があります。「掛け花」では花生けを正面壁や柱に掛けて、花器の正面からいける「向う掛け」、柱に掛けた掛け花生けの横からいける「横掛け」の二つに分けられています。
「吊り花」では、花器の形で、満月・三日月・舟などと言って。月を背景とした景観表現や、舟形の花器では、「垂真型」の(しん)を櫓に見立てるといった趣向が、今も残っています。▲
古典花の約束はともかく、「掛け花」・「吊り花」は、蔓ものなど下がる花材を思い切って使い、「平真型」・「垂真型」を基本にしながら、できるだけ自由な表現を試すことがおもしろいでしょう。 (Photo8・9)