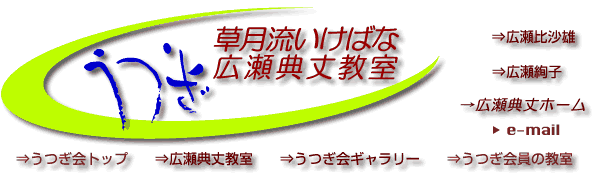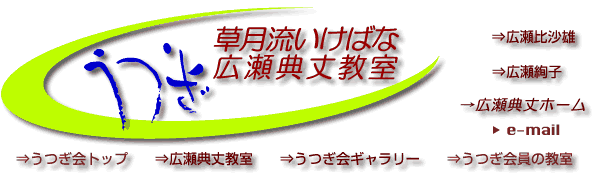(1)自然調の考え方「自然の模倣」
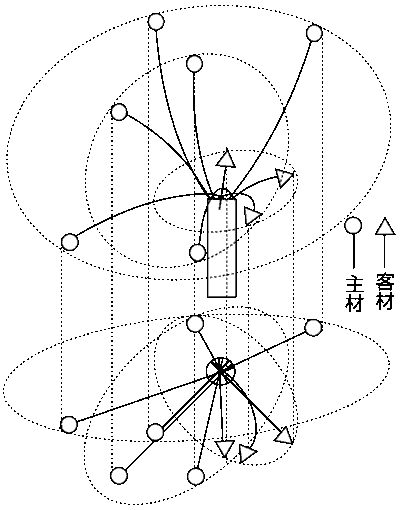 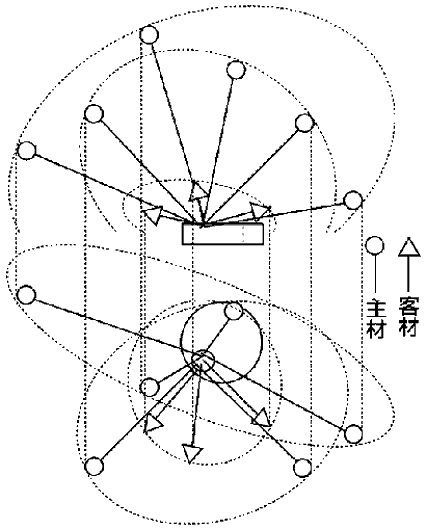 いけばなの「花型」では、基本的に、後ろに高く<木もの>(<枝もの>)の<しん>を置き、それより前に低く<草もの>の<下草>を置くというふうに作られて来ました。もっと踏み込めば、作品中心から2〜3本の役枝に沿って、長さと方向性を変えた枝を出していくという方法に絞られます。(右図)▲ いけばなの「花型」では、基本的に、後ろに高く<木もの>(<枝もの>)の<しん>を置き、それより前に低く<草もの>の<下草>を置くというふうに作られて来ました。もっと踏み込めば、作品中心から2〜3本の役枝に沿って、長さと方向性を変えた枝を出していくという方法に絞られます。(右図)▲
構成原理も「作為を隠して自ずから成るようにいける」「自然の模倣」「何気なさの典型」を祭る精神と要約できます。そういういけばなの構成法は、今では「自然調いけばな」と呼ばれています。
「古典花」や「自由花」の「自然調いけばな」は、すべてこの構成原理を使っています。
その方法をもう少しまとめてみましょう。▲
(2)「自然調いけばな」の構成法
  「自然調いけばな」の構成法を整理すれば、だいたい次の3つになります。▲ 「自然調いけばな」の構成法を整理すれば、だいたい次の3つになります。▲
1、<主材>(<しん>)と<客材>(<下草>)による時空遠近の対比
後ろに高く伸ばした<木もの>(特に常緑樹は永い時間性の表象)の<しん>と、その前下に加えた<草もの>(草花は瞬間の輝きの表象)の<下草>による遠近対比の構成です。▲
2、<骨法>(花型法)
<主材>(<しん>)を主に、数本の枝でいけばな全体の骨組みを作り、<客材>(<下草>の花で作品中心を作ります。
3、<出生>と<季節感>(「何気なさの典型」)
草木の自然に生えている姿を<出生>といい、<季節感>とともに尊重していけます。▲
(3)「作品中心」(視点)の深さ
  「自然調いけばな」では、「作品中心」(はじめに目が行き最後にもやはり目が行く、一番多く見る場所)の処理が重要です。「作品中心」は、作者(いけ手)と見る側の人の視点が重なる、共感の要になるポイントなのです。 「自然調いけばな」では、「作品中心」(はじめに目が行き最後にもやはり目が行く、一番多く見る場所)の処理が重要です。「作品中心」は、作者(いけ手)と見る側の人の視点が重なる、共感の要になるポイントなのです。
例えば、家庭でいける平均的な自然調の盛花では、作品中心を水盤の挿し口の真ん中少し上、投入では、挿し口の真ん中すぐ上に作るなど、いける側・見る側双方に暗黙の期待が生まれます。飾る場所や位置、見る人との 距離や動きも関係します。見る位置が高ければ「作品中心」は低く、逆に低ければ「作品中心」は高くしますから、飾り終えた後の補正も必要です。▲ 距離や動きも関係します。見る位置が高ければ「作品中心」は低く、逆に低ければ「作品中心」は高くしますから、飾り終えた後の補正も必要です。▲
「作品中心」の部分はまず前から、出来るだけ前後に深く取り、見る人が見通すような奥行きで整えることが大切です。
作例は、石化柳と乙女椿の2種いけですが、横から見た図・上から見た図でも分かるように、前後の奥行きがひじょうに深く取ってあります。(上Photo左は正面、右は右側面、下Photoは真上から見たところ。)▲
|