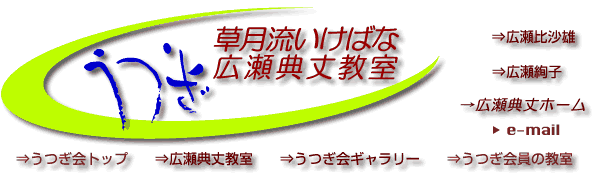(1)「自然調いけばな」との比較
 |
 |
| ↑→Photo1・2 ニューサイラン、ガーベラ、かえで
|
→「自然調いけばな」の構成法は、
1、「<主材>=<しん>による骨組み」
2、「<主材>=<しん>と<客材>=<下草>による遠近対比」、
3、「<出生>(生えていた時の状態)と季節感の尊重」、
という三つにまとめられます。(Photo1は「自然調」の作例。)▲
それに対して、「造形いけばな」は、欧米の芸術運動の影響によって生まれた新しいいけばなで、デザイン理論や彫刻などの手法を、いけばなにとり入れることから始まりました。
草木の「枝」「茎」「花」「葉」を、いけばな作品のための<素材>と考え、「線」「面」「塊」や、「色」「形」「質」を決める<要素>として扱うのです。まず「自然調いけばな」の三つの条件から離れましょう。▲
1、『主材で骨組みを作ら』ない、
2、『主材を高く後ろに、客材を短く前に』という構成法を使わない。
3、『出生や季節感』など、花材が担ってきた文脈を離れ、「枝」「茎」「花」「葉」を<素材>の<要素>として考える。
Photo2は、『ニューサイランで分割した線枠を作り、2つの枠内にそれぞれガーベラともみじを埋め込む』という構成です。
「造形いけばな」の練習方法はいくつかありますが、順を追って、まずここでは枠組みから考える方法を解説します。▲
(2)左右・上下・対角・交差など、構図を決めて配置する
  
↑Photo5 ぼけ、きんぎょ草
|
 |
| ↑Photo3 クルクマ |
↑Photo4 赤芽かしわ・あじさい・つつじ |
↑Photo6 こくわづる、カーネーション |
1、いけばなを置くスペースを左右・上下など、構図分割する。
2、草木の「枝」「茎」「花」「葉」を、1の構図に従って、対比的に配置する。▲
Photo3、左右、Photo4、上下、Photo5、対角、Photo6、交差と、とても単純な構成ですが、「自然調」のいけばなから離れる演習として、シンプルなものから、一つずつ、ステップを踏んで進んでいくことが大切です。▲
(3)粗密・主客・強弱の位置取り

↑Photo7 ふじづる、はらん |

↑Photo8 さざんか |
作品空間中の粗密・主客・強弱などの、位置取りも重要です。
Photo3の、クルクマの花と葉の左右の位置取り、Photo4も、赤と緑の葉で上下に配置されていますが、つつじの蕾を右に出すことによって、左に粗の空間が生まれます。Photo5のぼけと金魚草の作例では、右斜め上のぼけが粗、左下の金魚草が密の空間、Photo6の赤づるとカーネーションの交差でも、主客・強弱の捻るような位置取りが作品の印象を決めています。
Photo7は、左右も粗の空間を左上に取る作例、Photo8は、左下に取る作例です。ボリウム感や軽快感を確かめながら、実際にいけてみましょう。▲
|