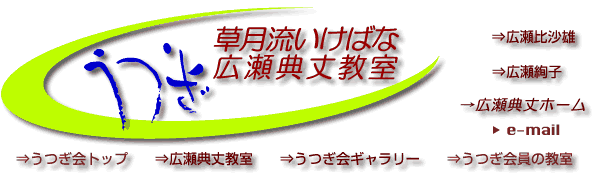
→広瀬典丈Webいけばな講座 →2 古典花→基本について →技術 →自然調とは →古典花
|
作例の「5枚活け」は「3枚活け」に<しん>前の従枝<胴>「右葉」と、<しん>後の従枝<見越し>「左葉」を加えました。<胴>は<しん>前にポリウムをつける従枝で、<しん>の葉柄を葉裏で包むようにして裏向きに差します。<しん>後の従枝<見越し>は、<そえ>と向き合うようにして、<しん>を支えます。「右葉」「左葉」の入れ方は、<しん>から<うけ>への中心線Lライン上に「右葉」、その外を支えるそえ葉が「左葉」。(逆勝手の場合はその反対)
<見越し>が<そえ>の仲間というのは分かりにくいかも知れません。中心線左上から入って右前へLラインを作る<しん>と<うけ>のグループに対して、<見越し><そえ>の仲間は右奥から左手前で中心線を支えるグループだと考えれば分かりやすいでしょう。
(3)はらん7枚活けと9枚活け
![]()
![]() 作例の「7枚活け」は「5枚活け」に<うけ内>「右葉」、<そえ内>「左葉」の従筏を加えています。
作例の「7枚活け」は「5枚活け」に<うけ内>「右葉」、<そえ内>「左葉」の従筏を加えています。
作例の「9枚活け」は、「7枚活け」に<うけしん>「右葉」、上乗を破って朽ち葉にした<うけ見越し>「左葉」を加わえました。
こうして加えていけば葉の数はいくらでも増やしていけますし、実際に15枚から数十枚いける流派もありますが、練習としては「9枚活け」までが限度でしょう。
▲