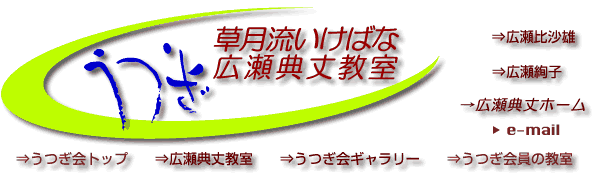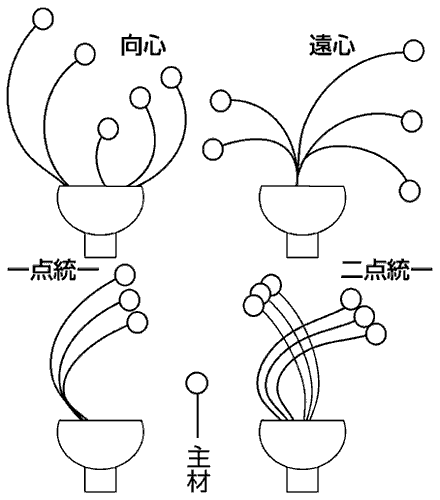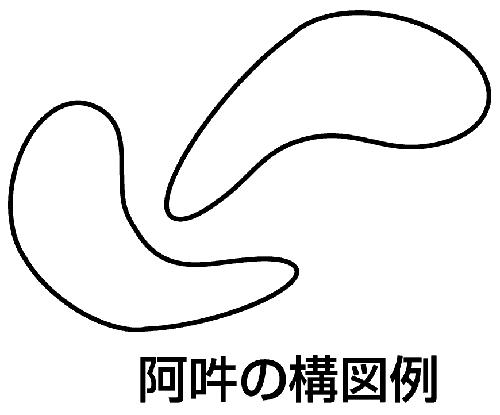↑Photo13 つくばねうつぎ
↑Photo14 あかめがしわ、 モンステラ、たますだれ
↑Photo13 つくばねうつぎ
↑Photo14 あかめがしわ、 モンステラ、たますだれ
|
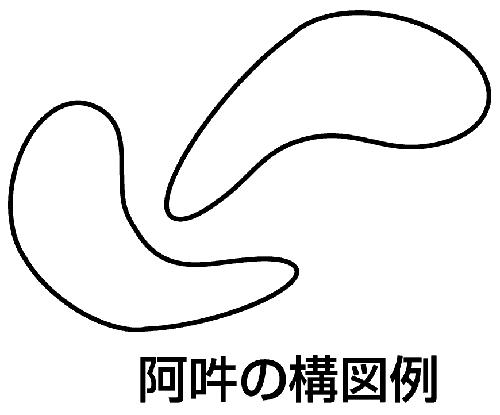 「自然調いけばな」を今度は「阿吽(あうん)の構図」という、少し違う角度から考えて見ましょう。 「自然調いけばな」を今度は「阿吽(あうん)の構図」という、少し違う角度から考えて見ましょう。
「阿吽」(あうん)というのは、「吐く・吸う」の呼吸を意味する仏教語で、庭や建物・絵画など「日本」のさまざまなシーンでその構成法を支えています。それは、左右や上下一対で、
1、「向かう・受ける」2、「凸凹」3、「粗密」4、「遠近」
などの間合いや構図を作っていく手法です。▲

↑Photo15 こでまり
→Photo16 はなしょうぶ、なつはぜ |
 |
いけばなの花型の<主材>(<しん>)と<客材>(<下草>)による構成も実はこの「阿吽」(あうん)なのですが、もっと構図的に考えると、「自然調いけばな」の→「株分け」や→「併合花」、さらに「座敷飾り」として書院や数寄屋を飾るときの、いけばなのバランス感覚なども、腑に落ちてきます。(参考図書として、『ジャパネスクの見方』西岡
文彦著作品社、1989年刊がお勧めです。)▲
Photo13は、つくばねうつぎの一種活けです。上から下に向かうつくばねを、下に並んだ葉が受ける構図です。Photo14は、併合花。グローブのようなモンステラの凹みが、下から上に延びる赤芽の凸部を受け入るような構図で、「向かう・受ける」の関係や「遠近」が分かりやすいでしょう。凸投・凹受どちらで遠近を取つてもかまいません。▲
Photo15・16は、「粗密・遠近の阿吽」の作例です。屏風・襖絵のように、4株で前後を取り左右で粗密を取りながら、後方に遠近がつくように、花も少し小さいものを選ぶと、遠近が強調されます。
|