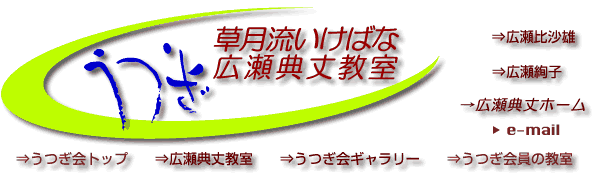
→広瀬典丈Webいけばな講座 →2 基本について3→基本について →技術 →自然調とは →古典花
|
いけばなは家の設(しつら)い「座敷飾り」として生まれました。設(しつら)いとは「室礼」(しつらい)、お客をもてなす礼式(神事)です。▲ いけばなの形も、「主材」(しん)と「客材」(下草)でいける「花型」、(しんの枝)=永遠性、(下草の花)=瞬間性という時空を祭る考え方が基になっていて、「木もの」と「草もの」を使っていけるのが基本です。→花材 ▲ |
1、「主材」(<しん><そえ>)が やや後ろから前斜め左側に偏り、「客材」<うけ>が「主材」の少し手前前斜め左側に張り出していること。 2、正面から見た時、 <しん>と<そえ>の間、<しん>と<うけ>の間が思い切って空いていること。 3、挿し口の前から厚く「客材」<うけ>が肉付けされていること。▲ |
(2)「役枝」(やくえだ)の長さ
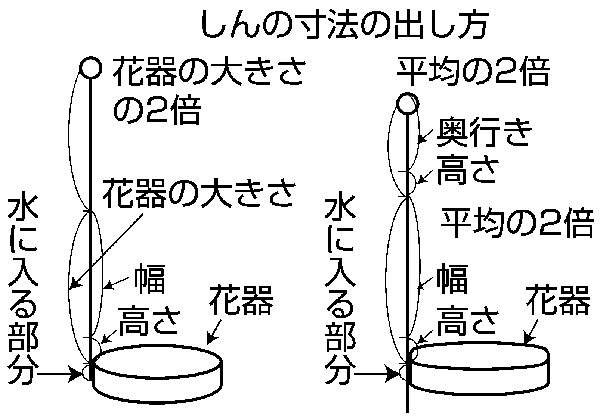 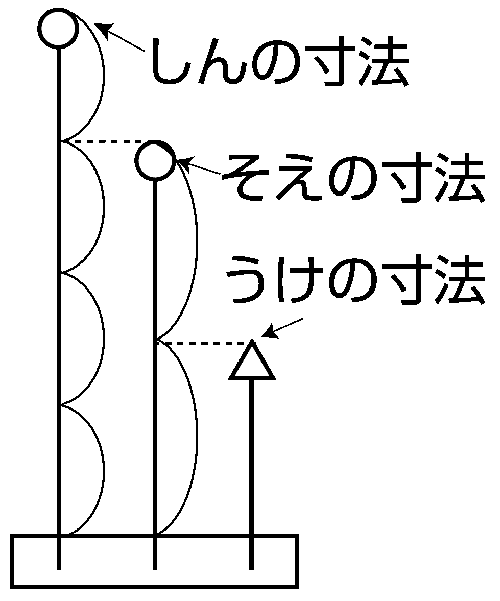 <しん>の長さは、花器から割り出すのが一般的で、「盛花」では、挿し口から上を、花器の大きさ(高さ+巾)の2倍程度に取ります。花器が長方形の場合には、(高さ+巾)と(高さ+奥行き)を足して、平均の2倍にしましょう。▲ <しん>の長さは、花器から割り出すのが一般的で、「盛花」では、挿し口から上を、花器の大きさ(高さ+巾)の2倍程度に取ります。花器が長方形の場合には、(高さ+巾)と(高さ+奥行き)を足して、平均の2倍にしましょう。▲これは挿し口から上の長さですから、必ず、水に入る部分を加えます。<そえ><うけ>の長さは、<しん>の長さから割り出します。これも、流派によって計り方が遠いますが、<そえ>は挿し口から上を<しん>の長さの3/4〜2/3、<うけ>は挿し口から上を<しん>の長さの1/3、または<そえ>の1/2で取ります。(図のマークは○が主材、△が客材) ▲ |
(3)「役枝」の方向性
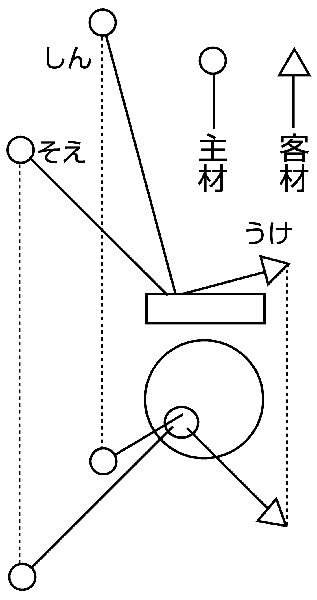 (しん)は<中心線>から左真半分45゜線までの左1/3辺りまで、<そえ>は左真半分45゜線まで前斜め半分まで傾けて留めます。一方<うけ>は右水平線から右真半分45゜線まで1/3上がる辺りに、前斜め、手前上から見た感覚では<そえ>と直角(実際は75゜くらい)に見える所まで傾けます。(左図) 3本の「役枝」を剣山に差すときの位置も、その方向性に合わせ、少し間隔を置くと肉付けを加え易くなります。(上Photo)▲ |
(4)花型の肉づけと作品中心(視点)の位置
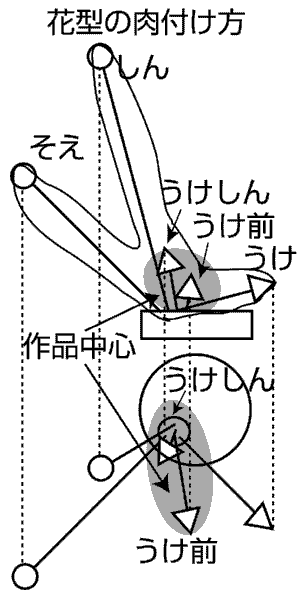 1、花型の肉付け
1、花型の肉付け
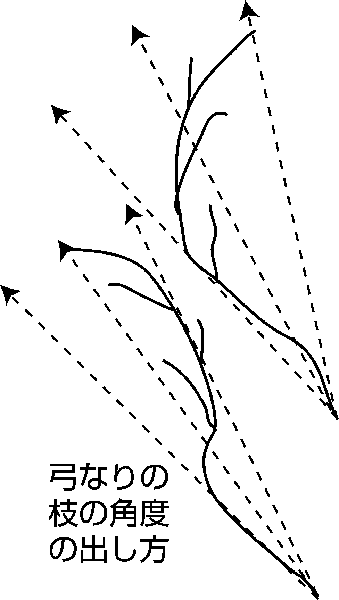 「花型」の肉付けで大切なのは、枝や花をどれだけ加えても、3本の「役枝」で出来上がった、「花型」のアウトラインを壊さないようにすることです。肉付けがその「役枝」よりも長くならないように、また、それぞれの「役枝」間に隙間を空けて、「花型」の枠組に収まるようにすっきりいけ上げましょう。▲
「花型」の肉付けで大切なのは、枝や花をどれだけ加えても、3本の「役枝」で出来上がった、「花型」のアウトラインを壊さないようにすることです。肉付けがその「役枝」よりも長くならないように、また、それぞれの「役枝」間に隙間を空けて、「花型」の枠組に収まるようにすっきりいけ上げましょう。▲
「主材」<しん><そえ>の枝のまとまりは、枝分かれを左右に広げず、前後に奥行きをつけて、それぞれをすっきりした線に見せるのがコツです。枝が曲がっているときの角度の取り方は、極端に考えられる弦と弧の2方向の平均で考えます。
「客材」に用いる花や→茂りは、全て<うけ>の肉付けです。「盛花」では、挿し口から水際あたりに花材を盛るようにいけます。▲
2、作品中心(視点)の位置
「作品中心」は、ぱっと目が行き一番よく見られる所で、そこが「客材」の位置になります。ただ、全体の骨組みを作る「役枝」の「うけ」は右端にあり、ふつうは「作品中心」ではありませんから、少し小さい花や蕾を使います。手前に突き出すように見る側に向かうものは、大きくて華やかな「客材」を用い、その後ろには少し短く上向きの肉付けを持ってきます。この2つを<うけ前><うけしん>、として「役枝」に加える流派もあり、そこを前後に見通すような深い奥行きでいけることが、いけばなの最重要ポイントです。▲
「作品中心」は、見る人の視点と重なりますから、飾る場所の高さや客との距離、視線の位置や動きも関係してきます。見る位置が高ければ「作品中心」は低く、逆に低ければ「作品中心」は高くし、飾り終えた後の補正も大切です。→(自然調作品中心)
照明などの光源の位置で花が動くこともあります。その場合は、無理にもとの位置に戻すのではなく、光源に合わせていけ直しましょう。 ▲
(5)「基本花型」をいける
   <しん><そえ><うけ>の順に、左上Photoの左・中・右のようにいけていきます。▲ <しん><そえ><うけ>の順に、左上Photoの左・中・右のようにいけていきます。▲その下Photoは、左から、<そえ><うけ>を入れたところの右側面。 中は、 <しん><そえ><うけ>を入れ終えたところの右側面。 右は。それを真上から見たものです。▲ 3つの「役枝」は、ふつうは先ず始めに入れます。 |
   次ぎに入れる順番は特にありませんが、
ここでは作品中心の<うけ前>と<うけしん>を入れています。Photoは左から、正面、右側面、真上。▲ 次ぎに入れる順番は特にありませんが、
ここでは作品中心の<うけ前>と<うけしん>を入れています。Photoは左から、正面、右側面、真上。▲次ぎに<しん><そえ>と肉付けし、 |
   最後に足元を整えて完成です。▲ 最後に足元を整えて完成です。▲剣山は仕掛けですから見せないようにします。茂りで隠せない場合には、小石などを敷いて隠しましょう。→完成作▲ |