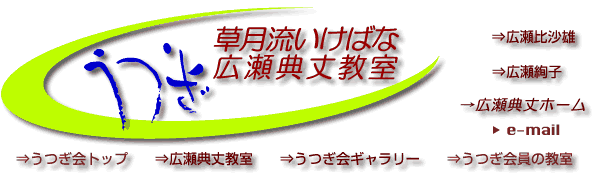(1)点の構成
    |
↑Photo1・2 姫みずき、
アンスリウム |
↑Photo3・4 ふじ、ライラック、
やぐるまぎく、デルフィニウム |
「点の構成」でぜひやっていただきたいテーマは、花器や枝などが作り出す空間の中に、大きさや数・位置を変えた点(花)をさまざまに置いて見る演習です。
1つの点、複数の点の大きさや色、位置どり、距離がもたらす<張力>(*注)の変化など、点が生み出す効果は複雑です。
動きやリズム、バランスなどを考えながら、同じ花材、異なる花材も使いながら、出来るだけたくさんいけて見ることがお勧めです。▲
(*注<張力>とは、点と点の間に働く心理的な力を言う。)▲
(Photo1・2は、左右黒赤の色分け花器に姫みずきを絡ませて、アンスリウムの花で点打ちしていく演習。
Photo3は、2つの花器を前後斜めに置き、左にライラックと赤紫やぐるま菊の同系色で前後の円を、右は藤と青紫やぐるま菊で上下に円を描く構図。
Photo4は、2つの花器の置き方縦横を変えて、ライラック・藤の枝を斜めに立ち上げ、下の3口花器には青みの強いデルフィニウムを置いています。(点打ちの演習については、→自然調3、→造形花1にも説明があります。▲
(2)線の構成
|
 |
  
|
| ↑Photo5 がま、とくさ |
↑Photo6 エニシダ |
↑Photo7 そてつ、
ふとい、グラジオラス |
枝・茎などの<主材>は、いけばなでは始めから意識された<線>です。
ここでは、ふだんは植物の形の中に隠れている線的な要素、枝・茎・葉、ときには花などのそれぞれが持っている独特の色・質・表情を取り出して、様々な構成を考えましょう。

|

|

←Photo8 晒しみつまた、ガーベラ、しろたえぎく
←Photo9水仙の葉
↑Photo10 あおもじ |
例えば、ふとい・とくさ・そてつのような、直線・曲線・リズムといった抽象的な動きに還元できるような花材もあります。▲
Photo5は、ふといをつなぐ手法で、屈曲した直線の動きを作り出しています。Photo6は、とくさに針金を入れて湾曲させ、曲線的な動きを重ねています。Photo7は、あらかじめ、そてつの葉を丸く引っ張って形を作り、リズム感よく放射状に延びた葉の線を見せています。
一方、Photo8・9・10のように、枝ぶりや葉の動きなど、その植物独自の<リズム>や<張力>、<弾力>を持った<線>を扱っていく工夫も楽しみです。
▲
|