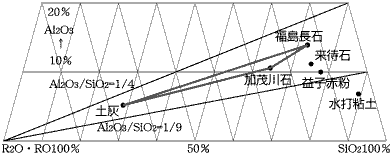(六)含鉄灰釉・土石釉の性状図
(1)『長石−土灰−藁灰系』+Fe2O3・MnO2
性状図
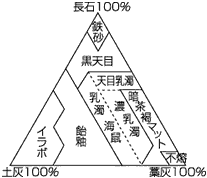
(図表30)長石-土灰-藁灰系性状図 1260℃RF
|
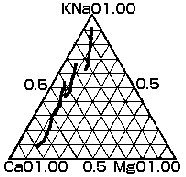
(図表31)塩基成分座標↑
画像2→
|

|
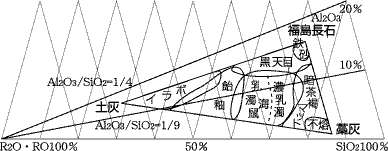
(図表32)含鉄灰釉の釉式座標による性状図(SK11RF) |
長石−土灰−藁灰系に紅柄(Fe2O3
)4%と二酸化マンガン(MnO2)2%添加したうわぐすりについて、その性状図の例を示します。(図表30・31
)(画像2)それを釉式三角座標によって表わしたものが(図表32)です。
これを見ますと、だいたい、長石の多い部分で 『鉄砂』〜『黒天目』、土灰の多い部分で『いらぼ釉』〜『飴釉』。それより藁灰の多い部分では乳濁『なまこ手』。藁灰のひじょうに多いところは不熔です。
▲
鉄砂 黒天目 飴 伊良保
長石←――――――→土灰 |
伊良保 飴 海鼠 不熔
土灰←―――――→藁灰 |
(図表33)長石−土灰−藁灰系の鉄釉の平衡
|
(図表33)左から、『鉄砂』というのは、うわぐすり中に赤鉄鉱が晶出したもの、
『黒天目』では、うわぐすり中に鉄イオンがほぼ熔融してFeの多い状態、『飴』ではFeが増えています。土灰が多いところで出る『伊良保』は、灰長石の結晶に鉄が少し加わったものが析出しているのです。藁灰が加わると再び鉄はうわぐすりに融けますが、さらに藁灰の珪酸が増えると、うわぐすりのガラス相は分離して(分相という)界面に結晶が析出します。これが『乳濁海鼠釉』です。海鼠釉の結晶はひじょうに小さく、コロイドと呼ばれ独特の性質を示します。▲
(2)『長石−土灰−含鉄土石系』性状図
長石−土灰−藁灰系の試験と並んで、長石−土灰−含鉄土石系のうわぐすり試験も、鉄釉を作る目的で古くから行なわれています。
日本で多く用いられる含鉄土石は、益子の赤粉・島根の来待石・京都の加茂川石・美濃の水打粘土などです。赤粉や来待石はそれ単味か少量の長石・土灰などと組み合わせて、還元焼成で『柿釉』『鉄砂釉』ができます。加茂川石は『黒楽』に使われています。それぞれ特色があって用いられ方も違いますが、共通にくくれる部分もあります。(図表34)
▲
|
K2O |
Na2O |
CaO
|
MgO
|
Al2O3
|
SiO2
|
Fe2O3 |
|
益子赤粉
モル
|
1.69
0.018
|
2.31
0.037
|
3.48
0.062
|
1.81
0.045
|
13.48
0.132
|
63.97
1.064
|
6.16
|
|
来待石
モル
|
1.02
0.011
|
2.07
0.033
|
4.68
0.083
|
1.64
0.041
|
16.11
0.158
|
59.92
0.997
|
5.72
|
|
加茂川石
モル
|
1.34
0.014
|
3.92
0.063
|
7.08
0.126
|
4.12
0.102
|
14.21
0.139
|
47.88
0.797
|
14.80
|
|
水打粘土
モル
|
1.44
0.015
|
0.39
0.006
|
0.29
0.005
|
0.82
0.020
|
7.52
0.074
|
59.85
0.996
|
12.01
|
↑(図表34)原料分析(『鉄釉』沢村滋郎より)
| 酸化物 |
Na2O |
K2O |
MgO |
CaO |
Al2O3
|
SiO2
|
P2O5 |
| 分子量 |
62.0 |
94.2 |
40.3 |
56.1 |
103.6 |
60.1 |
141.9 |
(図表35)成分酸化物の分子量 |
モル計算に 使用した成分の分子量は右のものです。 ▲
|
|
益子赤粉
|
0.92KNa O
0.03CaO
0.04MgO |
} |
0.94Al2O3・ |
5.31SiO2 |
|
塩基 12%
Al2O3 10%
SiO2 78%
|
| |
来待石
|
0.92KNa O
0.03CaO
0.04MgO |
} |
0.94Al2O3・ |
5.31SiO2 |
|
塩基 13%
Al2O3 12%
SiO2 75% |
| |
加茂川石
|
0.92KNa O
0.03CaO
0.04MgO |
} |
0.94Al2O3・ |
5.31SiO2 |
|
塩基 25%
Al2O3 11%
SiO2 64% |
| |
水打粘土
|
0.92KNa O
0.03CaO
0.04MgO |
} |
0.94Al2O3・ |
5.31SiO2 |
|
塩基 4%
Al2O3 7%
SiO2 89% |
←(図表36)釉式と、三成分モル%比 ▲
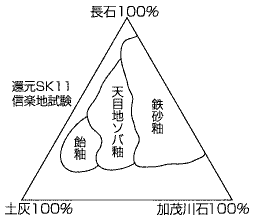 (図表37)長石−土灰−加茂川石系性状図 (図表37)長石−土灰−加茂川石系性状図 |
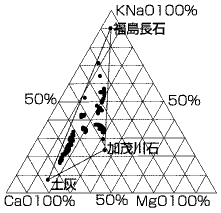 (図表38)塩基座標 (図表38)塩基座標 |
福島長石−土灰−加茂川石系の一部を三角座標による性状図を示しましょう。
(図表39)を見ればわかるように、含鉄土石の組成は、塩基成分を考慮しなければ長石と陶石の中間位置にあり、これらの三成分系の試験は、アルミナ・珪酸分の多い長石−含鉄土石と、塩基成分の多い土灰の間の直線的な置換試験と考えて差し支えありません。▲
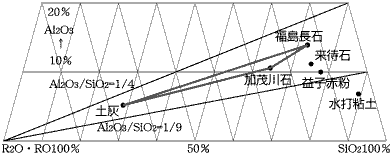
(図表39)釉式座標による含鉄土石釉の組成位置 |
おそらく、自然降灰釉から始まった高火度釉にどのような土石を加えてうわぐすりを安定させるかは、長石・陶石に限ったことではなく、熔融温度の低い含鉄土石は長石と同じように使われてきたのでしょう。事実、鉄釉と呼ばれるものの多くは含鉄土石−土灰系の置換で得られるもので▲
福島長石−土灰−加茂川石系も、その意味で(図表32)の性状図から大きく踏み出すものではありません。ただ『鉄砂』の範囲が広がり、天目地に蕎麦釉の結晶が出るところが少し違います。これは塩基に原因があります。(図表38)の塩基の三角座標を見ますと、アルカリの多い長石、石灰分の多い土灰に対して、加茂川石がかなりマグネシア分を多く含んでいることが分かります。釉の塩基成分に含まれるマグネシア分が、うわぐすり中に結晶を作りやすくさせているのです。ちなみに、蕎麦釉の結晶は鉄とマグネシアを含む輝石系のものです。
以上で、うわぐすりを塩基−Al2O3 −SiO2三成分系と塩基成分で見ていくという立場の説明ができたと思います。それはうわぐすりをそのガラスとしての化学的性質を通して考えるということなのです。▲
<主な参考文献>
『釉調合の基本』加藤悦三著‥‥窯技社
『鉄釉』( 其の1ー4)沢村滋郎‥‥窯業協会誌48(1940)
『三角座標による磁器釉組成の考察』加藤悦三‥‥窯業協会誌70(1962)
『陶磁器における鉄の呈色』加藤悦三‥‥化学工業(1980 年10月号)
『鉄釉の研究』名工試報告11-8〜14-17 ↑
『高火度釉基礎試験』編集発行-釉研究会書記局(1976)
\1600
残部があります。ご注文は下記まで。
郵便振替口座=00870-6-33157 広瀬典丈 e-mail
→1高火度釉に対する考え方
→2うわぐすりの化学 →3化学結合の性質
→4珪酸塩ガラスの構造 →5釉式座標による灰釉性状図
→7釉式計算の仕方
→8釉式を使った釉調合の方法 →9長石-CaO-BaO-MgO-ZnO系透明釉性状図
→10長石-CaO-BaO-MgO-ZnO系+Fe2O3性状図
|

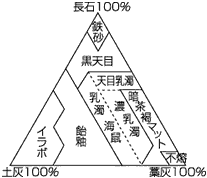

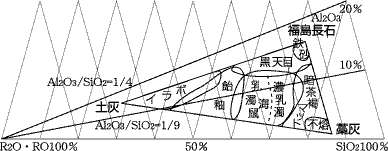
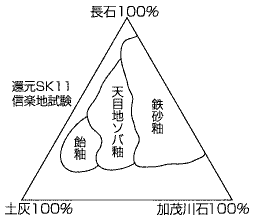 (図表37)長石−土灰−加茂川石系性状図
(図表37)長石−土灰−加茂川石系性状図 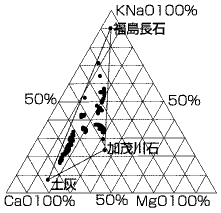 (図表38)塩基座標
(図表38)塩基座標